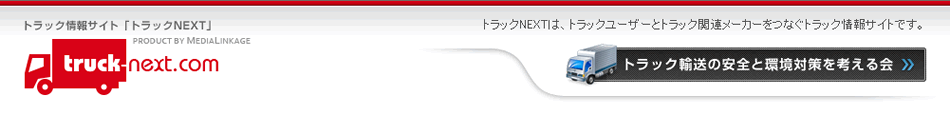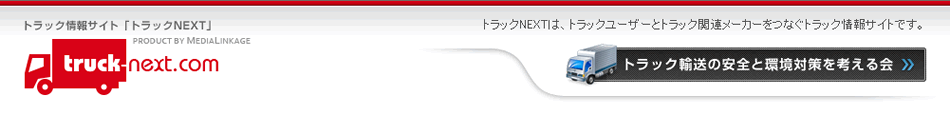|
平成22年5月18日、政府は20日から開催される事業仕分け第2弾後半戦の対象事業を正式に発表した。
仕分け対象は、日本宝くじ協会の「宝くじの普及宣伝事業」や全日本交通安全協会の「運転免許の更新時講習」など、国が事業を委託したり権限を付与したりする、政府の関与が強い公益法人の中で、天下りの人数が多い法人や無駄が多いと判断した法人を中心とする公益法人など70法人82事業となった。
今回、緊急特集として、特別ページを掲載するにいたった経緯としては、この仕分け対象に異例とも思える業界団体であるはずの全日本トラック協会が選定されたからだ。
対象となった事業は、行政刷新会議のホームーページは1行だけ「都道府県トラック協会からの出捐金(しゅつえんきん)による事業」とある。
出捐を調べると「寄付すること」「当事者の一方が自分の意思で、財産上の損失をし、他方に利益を得させること」とある。
つまり、今回の場合の「出捐金」は、都道府県トラック協会から全日本トラック協会に拠出される支払いを指すことになる。
ここで、この「出捐金」とはいかなる性格のものなのか、なぜ支払うことになったのか?その経緯を解説しよう。
事の発端は1976年、今からさかのぼること34年前に成立した道路特定財源に充てる道路整備費財源特例法(いわゆる道路特定財源)だ。
この道路特定財源は2008年に改正され、軽油が安くなったり高くなったり・・・。トラック運送事業者にとっても多大なる影響を及ぼしたことは記憶に新しい。詳細は別ページを設けたので参照してほしい。(道路特定財源について)
さて、この道路特定財源。新しい道路を作ったり、整備するのにお金がかかる。これまでの税金ではとても足りないということから道路を作ったり整備するためだけに使える税金を作った。これが道路特定財源だ。
それでも足りなくなったので、1976年に道路特定財源の中の自動車・トラックに関わる税金を期限付きで引き上げた。これを暫定税率といい、1993年にさらに税率を引き上げて延長され、その後1998年、2003年と延長されてきた。
国に収納されるものとしては 「揮発油税」 「石油ガス税」 「自動車重量税」があり、地方(各都道府県)に収納されるものとしては 「地方道路譲与税」 「石油ガス譲与税」 「自動車重量譲与税」 「軽油引取税」 「自動車取得税」
がある。このうちトラック運送事業に大きく関わるのが「軽油引取税」だ。現在、暫定税率として30%引き上げられており、 2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられている。
当時、当然ながら運送業界は引き上げに猛反対した。結局対応策として、軽油引取税の中から国が定めた計算式に基づいて計算された金額を各都道府県から各都道府県トラック協会に交付金として支払われることとなった。それが運輸事業振興助成交付金だ。
この交付金を 「トラック運送事業の近代化」「合理化等のための低利融資事業」「輸送情報ネットワークの確立のための事業 」「交通安全対策、環境対策等の事業」のために活用するという目的で合意された。
結果、 各地のトラック協会では加盟する業者への融資や借入金に対する利子補給のための基金として積み立てられ、その一方で各トラック協会は、交付金の約25%を全ト協が運用する基金にも適用することとなった。
この交付金の約25%の「出捐金」が、今回の事業仕分けの対象となったのである。
問題視されるのは、その金額の多さからであることは否めない。当然ながら額が額だけにダークな噂も流布される。1例を挙げれば政治献金への転用だ。
ここでは、「噂」をつらつらと書き綴る気はない。もし「噂」が本当であるならば、断固糾弾されるべきであるし、事実無根であるならば正々堂々と主張すればいい。
| ニュースサイトとしては、いささか逸脱した行為かもしれないが、ここからは筆者の体験や思いを書きつづらせていただくことをご了承いただきたい。 |
まず、「天下り」についてだ。インターネットで調べてみたところ、04~06年度に国土交通省10人、内閣、総務、警察の3府省庁からそれぞれ1人、合計で13人が全ト協と都道府県のトラック協会に天下りしているという。当編集部ではそのうち少なくとも5人を良く知っているが、何が問題なの?と言いたくなるほど皆まじめに仕事している。特に全ト協の部長にいたっては、毎日夜9時10時まで仕事をしていることはザラで、終電まで残業することも珍しくない。偶然かもしれないが、夜11時に送信したメールに即時返信されたことには少々驚いた経験がある。また同部長はプライベートな酒の席には顔を出さない。何度お誘いしても、丁重にお断りされる。当然仕事にも熱心で、メーカーの新製品発表会や物流関連セミナーでよくお会いする。会場までは電車・バスを使い、それもプレスや一般の来場者に混ざって参加されており、特別扱いはされていないので、全ト協の部長さんとは誰も気づかない。
少なくとも、全ト協や都道府県のトラック協会において、何の生産もせず、VIP待遇で海外研修をしたり、2~3年在籍して退職金をもらって他の団体に転籍する、いわゆる「渡り」といわれるような「天下り」を筆者は知らない。
次に運輸事業振興助成交付金の使い方だ。弊社では「トラック輸送の安全と環境対策を考える会」を主管しており、これまでに全国各地のトラック協会で交通安全対策、環境対策助成金の対象製品の展示会を開催してきた。今年も、6月28日に群馬県館林支部、6月29日に静岡県トラック協会で開催することが決定している他、鹿児島・大分・長崎・山口・神奈川・山梨・群馬のトラック協会から展示会開催の希望がある。
トラック輸送における交通安全対策、環境対策は深刻で、大型トラックによる死亡事故などは、まるで社会の悪のようにマスコミで大きく取り上げられる。運送業者はただでさえ不景気の影響で仕事が激減し、苦しい経営を余儀なくされる中、それでも1件でも事故を未然に防ごうとドライブレコーダーやバックカメラなどの事故防止機器の導入を推進している。この機器が全車に装着となると馬鹿にできない金額になるのだ。助成なくして機器の導入は困難であろう。
さらに、トラック運送業界は99%以上が中小零細企業のため、安全対策をはじめとした事業の適正化が求められている。そのため、業界独自で「貨物自動車運送適正化事業」として適正化指導員による巡回指導や「安全性評価事業(Gマーク制度)」を推進している。
前述の事故防止対策・環境対策にしても然り、新しいトラックに買い替えるにしても、基金を担保にした融資制度がなければ銀行は金を貸してくれない。当然ながら年数の経った車輌はそれだけで事故に直結する故障がおこる頻度が高まることは小学生でも分かる原理だ。
全ト協に集まる出捐金も、14兆円という市場規模、そして毎年1兆円もの車輌を購入している投資規模から考えれば決して多額とも言えないと思うし、融資等の担保として融資額の3倍の基金が必要という商工中金とのルールを考えれば、基金残高の妥当性は十分だ。
最後になるが、多くの運送業者では事故防止対策・環境対策を施したくとも助成や基金の担保がなければ無理であり、それどころか事業存続すら危ぶまれる経営環境化にあるという背景を忘れてはならない。
もちろん、これらの事業以外にこの交付金が使われているのならば言語道断だ。徹底的に糾弾されるべきであろう。この辺が今回の事業仕分けの争点になるのだと思われるが、正々堂々と上記4つの事業の必要性、妥当性を主張してほしい。
|